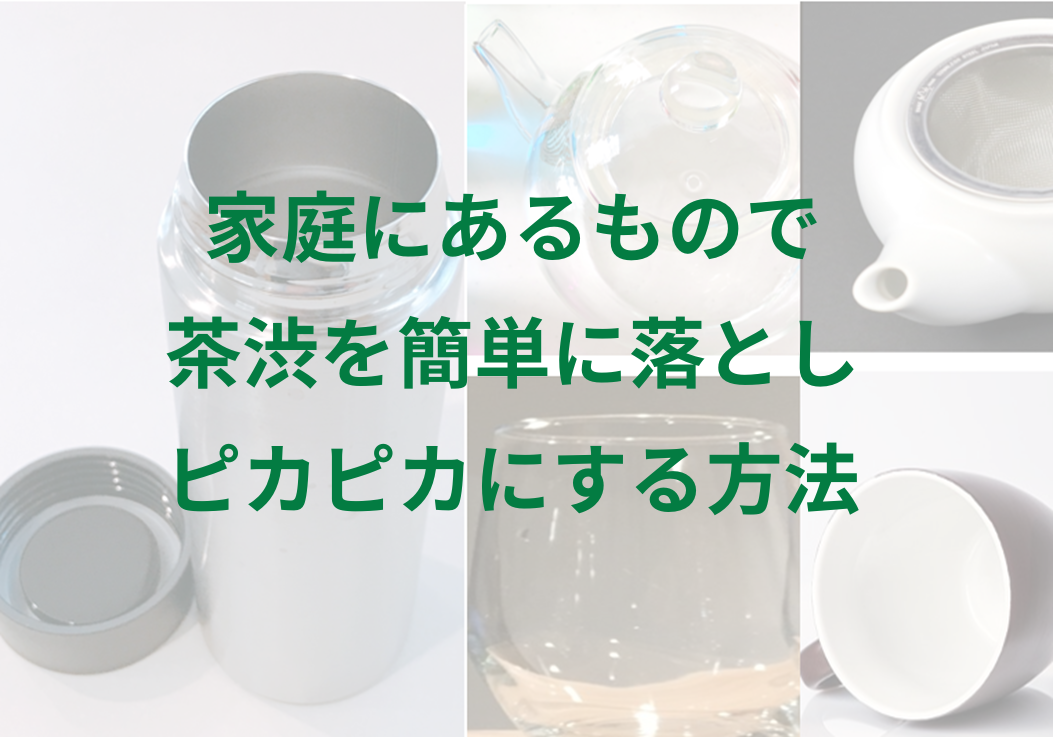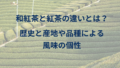毎日使う水筒や茶器に付着する茶渋は、放置すると落としにくくなります。
しかし、家庭にある身近なアイテムを活用すれば、きれいにすることが可能です。
今回は、茶渋の原因と素材別の落とし方についてをご紹介します。
茶渋の原因と対策

茶渋が付着する原因とメカニズム
茶渋は、お茶に含まれる渋みのもとタンニンが酸化し、水垢やミネラル分と結びつき、固まって付着することで発生します。特に長時間放置してしまうと蓄積して落としにくくなります。
茶渋は色素だけではなく、汚れとなって付着している状態といえます。
クレンザーや金属タワシなどでこすってしまうと、細かな傷ができてその部分から、余計に茶渋がつきやすくなってしまうため、避けた方がよいでしょう。
茶渋汚れを防ぐ予防方法
茶渋の付着を防ぐには、使用後すぐに洗う、もしくはお湯を通して乾燥させることで、ある程度可能です。
さらに、定期的な重曹やクエン酸洗浄を取り入れることで、長く清潔に保つことができます。
家庭で茶渋を落とす方法

家庭にある重曹やクエン酸、塩などを活用することで、茶渋は落とせます。使用後は水ですぐに洗うとともに、頑固な茶渋になる前に定期的にこれらを用いるとよいでしょう。
また茶器に関しては、茶葉の香りに影響を与えないよう、すすぎを十分行うとともに、無香タイプの台所用洗剤を使うとよいといわれています。
重曹を使った茶渋落とし
重曹(炭酸水素ナトリウム)は弱アルカリ性で、酸性の茶渋を分解する作用があります。40~50℃程度のぬるま湯1Lに重曹大さじ2~3ほどを溶かして数十分~1時間ほど浸け置き、スポンジでこすると細かい部分の汚れもすっきり取れます。
頑固な茶渋には、特に熱湯に溶かして数時間浸け置きすると取れやすくなります。
また茶渋部分にそのままふりかけるか、ペースト状にして塗布し、しばらく置いてからこすると、研磨作用によって落とすことができます。
クエン酸や酢を使った茶渋落とし
クエン酸や酢の酸の力で、たまったカルシウムやミネラル成分を緩める作用があります。
水垢と汚れがたまった茶渋の場合、水筒や茶器に直接クエン酸を記載の分量通りに入れ、お湯で溶かしてしばらく置いてからスポンジでこすることで、すっきりします。
酢を使う場合は、水と酢を1:1の割合で混ぜた溶液を作り、茶器や容器などを入れてに注いで数十分置いてスポンジでこすります。特にガラス製の食器の場合は、くもりもとれてピカピカになります。
※鉄製品は酸と反応して変色やサビの原因になってしまうため、使用は控えましょう。
塩を使った自然派の茶渋落とし
塩には研磨作用があり、茶渋をやさしく削り取ることができます。スポンジに少量の塩をつけて弱い力でこすります。
酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を使った茶渋落とし
過炭酸ナトリウムは酸素系漂白剤の成分で、強アルカリ性により茶渋の酸化汚れを強力に分解します。40~50℃のお湯に溶かして浸け置きした後、スポンジでこすります。
また、跡が残らないよう洗浄後はしっかりすすぎ、乾燥させておきましょう。
※陶器など素材によっては使用できない場合もありますので、ご注意ください。
その他の茶渋掃除アイテム
メラミンスポンジ
メラミンスポンジは微細な繊維で汚れを削り取るため、力を入れずに茶渋を落とせます。ただし、強くこすると傷がつくこともあるので注意が必要です。コーティングや絵付けのある製品は、はがれてしまう場合があるため、使用は避けたほうがよいでしょう。
アクリルたわし
アクリルの細かな繊維が汚れを掻き出してくれます。傷がつかないようやさしい力加減で少しずつこすりましょう。高級陶器など、繊細な材質の製品は避けた方が無難です。
歯磨きペースト
歯磨きペーストには研磨剤が含まれており、茶渋を無理なく落とせます。様子を見ながら、指やスポンジでやさしくこするとピカピカになります。
塩素漂白剤と注意点
塩素系漂白剤は、刺激も強いため換気をしながら使用し、しっかりすすぐ必要があります。また、陶器やメラミン樹脂、金属製品には使用できないことが表記されているためご注意ください。
素材別水筒や茶器の茶渋の取り方

ステンレス製水筒やタンブラーなどの場合
ステンレス製水筒やタンブラー、茶こし類は、重曹や酸素系漂白剤を使うと、内部の茶渋をしっかり落とせます。
40~50℃程度のぬるま湯に重曹を溶かして数時間置くと、汚れを浮かせることができます。その後、茶こしの網目など細かい部分は柔らかい歯ブラシを使うと、隅々まで掃除できます。
水筒は、500mlサイズに重曹大さじ1程度を目安に入れ、熱湯を注ぎ発泡させ1時間ほど置いてから、蓋をして振ります。その後、お湯を捨てブラシなどで中を洗います。
水垢を伴う白い汚れなどが残っている場合は、クエン酸を熱湯で溶かし1時間ほど置いて汚れが緩んだ後、ブラシなどで中を洗います。
プラスチックや樹脂製コップの場合
プラスチックや樹脂は傷つきやすいため、重曹と少量の水を混ぜた重曹ペーストを指先や柔らかいスポンジにつけてこすると、傷をつけずに汚れを落とせます。
もしくは、ぬるま湯を張って重曹を溶かし、1時間ほど置いてから、スポンジで優しくこすり洗いをします。
漂白剤を使用する場合は、酸素系漂白剤を選びましょう。
ガラス製の茶器やコップなどの場合
酸素系漂白剤、もしくは酢と40~50°のぬるま湯1:1の溶液の中に、数十分~1時間つけ置きしたあと、柔らかいスポンジでこすり、水で十分すすぎ乾燥させます。
フタ裏のふちやポットの注ぎ口など、細かい部分は綿棒などを使うときれいにとれます。
陶器製の茶器などの場合
塩や歯磨きペーストを使い指や湿らせたスポンジで少しずつこすると、細かい粒子で陶器を傷めずに茶渋を取り除くことができます。
高級茶器など以外であれば、水で濡らしたメラミンスポンジを使用するのも便利です。
また、40~50℃程度のぬるま湯1Lに重曹大さじ2~3ほどを溶かした重曹液に数十分~1時間ほど浸けた後、スポンジや細い注ぎ口は綿棒もしくは専用の細いブラシなどでやさしくこすると、きれいになります。そのあと水で十分にすすぎましょう。
※メーカーによっては、酸素系漂白剤の使用も推奨していない場合があるので取扱説明書などで事前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ

茶渋は、お茶の中のタンニンが酸化し水垢やミネラル分と結びつき、固まって付着することで発生する色素のついた酸性汚れです。
付いてしまった茶渋は、家庭にある重曹やクエン酸、塩などを活用することで落とすことができます。
その場合、汚れの程度や素材に合わせて選ぶことが重要です。例えば、軽い茶渋には塩や歯磨きペーストなどを使った方法が手軽で便利ですが、頑固な汚れには重曹や酸素系漂白剤を活用したつけ置き洗浄、水垢も重なった茶渋や全体的なくもり汚れにはクエン酸を使用するとよいでしょう。
また、茶渋を防ぐためには、日頃からのこまめな洗浄が欠かせません。使用後すぐに洗って十分乾燥させることで汚れが定着しにくくなり、より手間をかけずに清潔な状態を維持できます。その上で、定期的に重曹やクエン酸での洗浄を行うことで、水筒や茶器をより長く快適に使用することができます。
毎日の習慣としてすぐのお手入れと、適切な掃除方法を活用することで、気持ちよくおいしいお茶をいただきましょう。