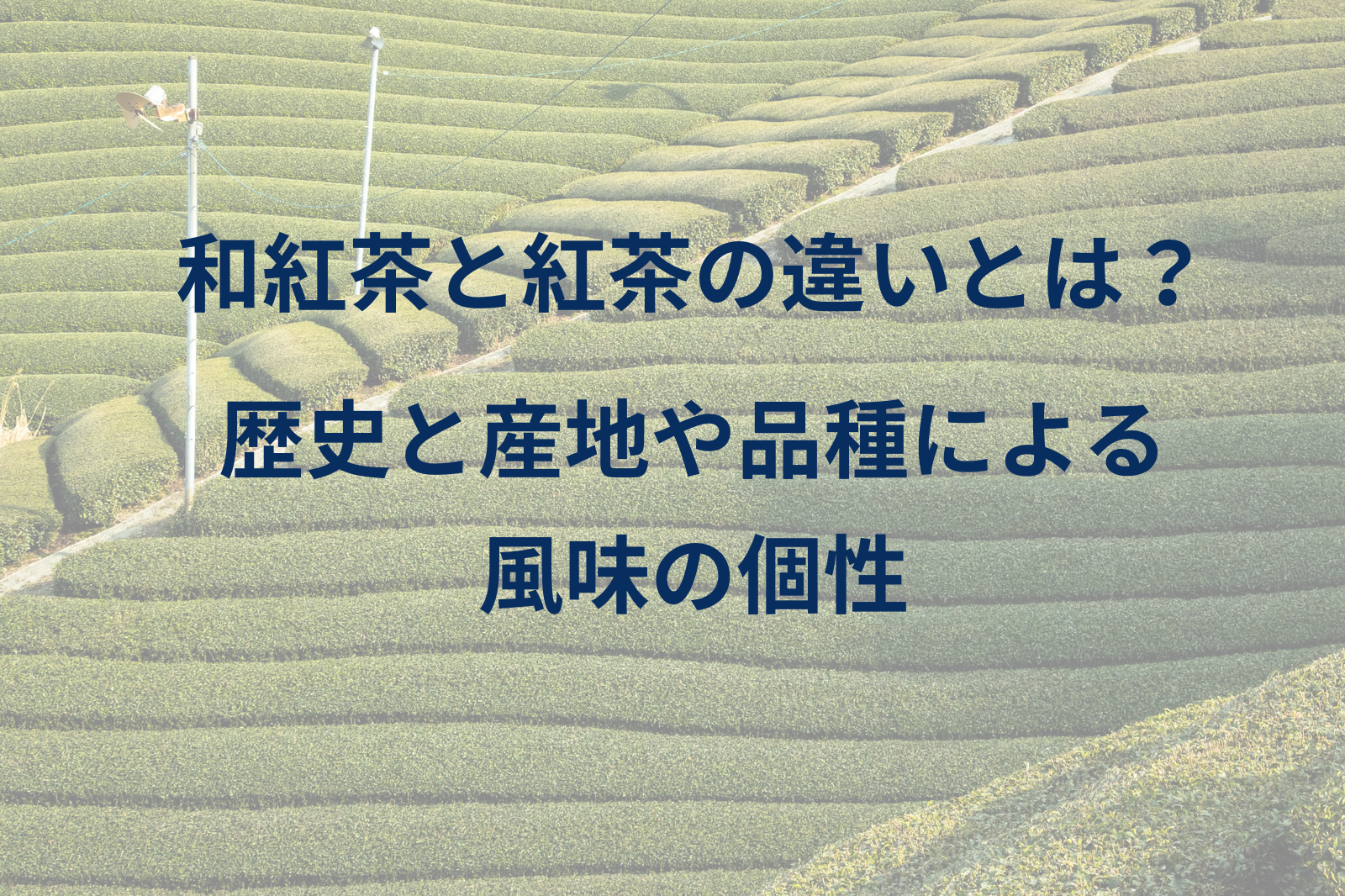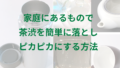紅茶といえば、インドやスリランカを思い浮かべる方も多いかもしれませんし、日本でお茶といえば緑茶じゃないの?と思うかもしれませんが、日本国内において「和紅茶」と呼ばれる紅茶が作られていることをご存じでしょうか?
和紅茶は、日本で栽培された茶葉を使用し、日本独自の製法で作られた紅茶です。
近年では生産地ごとに異なる個性を持つクラフト感覚の多様性を持ち、海外産の紅茶とはまた異なる魅力が注目されています。
こちらでは、和紅茶と一般的な紅茶の違いや、生産の歴史と産地や品種による風味の個性について調べ、まとめてみました。
和紅茶と紅茶の違い

紅茶とは?
紅茶とは、ツバキ科ツバキ属のチャノキ(学名:カメリア・シネンシス)の茶葉を、完全に発酵させたお茶です。
主にインドやスリランカ、中国などを中心にティーベルトと呼ばれる各国の産地で生産され、茶葉の種類と産地ごとに異なる風味や香りを楽しむことができます。たとえば、インドのダージリンは華やかな香りと爽やかな渋みが特徴であり、アッサムは濃厚でコクのある味わいが楽しめます。スリランカのセイロン紅茶は柑橘系の爽やかな香りを持つことが多い傾向にあります。
※世界の紅茶産地やチャノキの種類などに関して、詳しくはこちらをご覧ください。茶の木の主な2種が育つ紅茶の産地「ティーベルト」とは?
和紅茶とその特徴は?
「和紅茶」とは、日本国内で栽培された茶葉を使って製造された紅茶のことを指し、「国産紅茶」や「地紅茶」とも呼ばれています。
日本の茶葉を使用しているため、日本茶に近い風味を感じることもあり、穏やかな香りと口当たりの良さが魅力です。
さらに、日本ならではの気候や土壌が、和紅茶の個性を生み出しています。寒暖差の激しい地域で育った茶葉は、甘みが増し、より深い味わいとなり、標高の高い場所の茶葉は、繊細で上品な香りを持つ傾向があります。こうした地理的要素と栽培技術の組み合わせによって、多様な和紅茶が生み出されています。
和紅茶は、その優しい風味と繊細な香りから、日本茶に慣れ親しんでいる人にも親しみやすく、また海外の紅茶とは異なる魅力を持つ紅茶として、国内外で注目されています。
和紅茶と紅茶の味わいと香りの違い
海外産の紅茶はコクや渋みが強い傾向にありますが、和紅茶はおおむね穏やかで飲みやすい風味が特徴です。
また、近年はチャノキの中国種のみならず、アッサム種との掛け合わせをはじめとした新たな品種、産地や製造方法によって異なるフルーティーな香りや、和の趣を感じさせる独特の甘みなど、多様なクラフト感を楽しむことができる傾向にあるようです。
紅茶特有のタンニンの渋みが少なく、ストレートで飲んでも優しい口当たりのものが多い傾向です。
和紅茶の歴史と生産地や品種による個性

日本茶と紅茶の違いとつながり
日本茶(緑茶)と紅茶は、どちらも「カメリア・シネンシス」という同じ茶の木から作られますが、製造方法の違いで異なる味わいになります。
特に発酵の度合いや加工方法によって、日本茶の爽やかさと紅茶のコクが生まれます。例えば、煎茶は茶葉を蒸して発酵を防ぐことで緑色を保ちますが、紅茶は茶葉を完全に酸化させることで深い琥珀色の水色と独特の香りを生み出します。
日本のお茶農家は、地域ごとに異なる製茶技術を持ち、伝統的な手法と現代的な技術を融合させて和紅茶を生産しています。製造工程では、茶葉の萎凋(いちょう)、揉捻(じゅうねん)、発酵、乾燥といった工程を丁寧に行い、茶葉本来の風味を引き出します。特に、発酵時間の調整によって、フルーティーな香りや花のような甘みを持つ紅茶が生まれることもあります。
※製造工程ついて、詳しくはこちらをご覧ください。六大茶分類から知る緑茶・ウーロン茶・紅茶などの違いとは?
和紅茶の誕生とその背景
中国からチャノキの種とともに緑茶が持ち込まれたのは、奈良時代といわれています。はじめは薬用に用いられ、安土桃山時代には茶道として日本独自のお茶文化が展開され、幕末にはヨーロッパにも輸出されていきました。
そしてイギリスから日本に紅茶が持ち込まれたのは、明治時代にさかのぼります。当時、日本では政府主導で輸出用に紅茶の生産が始まりましたが、海外の紅茶との競争、品質や生産量およびコスト面などから一時生産は下火となり、昭和40年代(1970年代)の輸入自由化により産業化は停滞していました。
その後、2000年頃から国内消費を中心とした需要の高まりに応じて和紅茶の生産者が増加し、再び注目されてきました。特に、日本の茶葉にこだわる消費者の増加やメディアによる特集などにより、和紅茶の人気を後押ししています。
国内生産地と特徴ある品種
この10年ほどで和紅茶の国内生産地は2倍以上に増加し、全国各地で300以上の生産者により生産されているそうです。
特に鹿児島、静岡、宮崎、京都など緑茶の産地と重なる地域が有名で、それぞれの土地の気候や土壌が独自の風味を生み出し、地域ごとの違いを楽しむことができます。
また、在来種であるチャノキの中国種以外に、アッサム種との交配種や品種改良などによる日本の紅茶用品種の開発が進み農林登録も複数なされているそうです。
発酵を抑えめにして強い渋みを抑え自然な甘さや香りの個性を伸ばすような製法など、生産者によるクラフト感覚に富んだ個性豊かな和紅茶が生産されるようになりました。
まろやかで繊細な味わいと、柑橘系のフルーティーな香りや花のような香りを持つものなど、多様な風味を楽しめます。
生産時期
国内の茶葉生産時期は、緑茶の時期とほぼ同時期です。
和紅茶は、一番茶:4月末~5月中旬、二番茶:6月中旬~7月、三番茶:8月のうち、主に二番茶の頃の気候が発酵も進むため適しているそうです。
おもな品種別の和紅茶の特徴
国内の紅茶産地では、主に以下の品種が栽培されています。
- やぶきた:日本の緑茶の約75%を占める代表的な中国種系の在来品種。和紅茶としても加工され、渋みが少なくスッキリとした味わいと爽やかな香りが特徴。
- べにふうき:静岡産の紅茶・半発酵茶向けに開発されたアッサム種を源とする品種。しっかりした渋みと濃厚なコク、フルーティーな香りが特徴。ミルクティーにも適している。
- べにほまれ:日本で最初に開発された国産紅茶品種(茶農林1号)で、豊かで甘い香りと深いコクが特徴。
- べにひかり:日本で開発されたアッサム系紅茶品種で、スパイシーでウッディな香りがあり、個性的な風味を持つ紅茶向きの品種。
- さやまかおり:埼玉県を中心に栽培される中国種系の早生品種で、緑茶のような爽やかさと濃厚な渋みやうま味と強い香りが特徴。花のような香りを持つものも。
和紅茶の人気と世界での注目
近年、和紅茶は国内外で注目を集めており、日本の高品質な茶葉を使った紅茶として、海外の愛好家からも評価されています。
特に、ヨーロッパでの日本の食文化への関心の高まりや、ティーコンテストで高い評価を得た和紅茶も増え、今後さらなる注目が期待されています。
和紅茶に合う飲み方
和紅茶の味わいは、茶葉の品種によって大きく異なります。
例えば、「べにふうき」はしっかりとしたコクと渋みがあり、ミルクティーに適しています。一方で、「やぶきた」を使った和紅茶は、すっきりとした味わいでストレートティーに向いています。また、「さやまかおり」や「べにほまれ」などの品種は、それぞれ独特の香りや甘みを持っており、飲み比べる楽しさがあります。
ハーブ類や他の茶葉、果皮などのフレーバーとブレンドする場合も、調和しやすいといわれています。
また、和菓子との相性もよいようで、例えば、羊羹やどら焼きの甘さと和紅茶のまろやかな風味がよく合います。一方で、洋菓子やチーズと、チョコレートやナッツと組み合わせると、紅茶の甘みやコクが引き立ちます。
茶葉やティーバッグ、水出し用やペットボトルなど、日常に取り入れやすい商品が多く、気軽に飲むことができます。
まとめ

和紅茶は、日本国内で茶葉を栽培製造され、日本ならではの製法と産地特性や品種を活かした、優しい甘みと繊細な味わいや豊かな個性が特徴の紅茶です。
国内生産は明治時代に始まり、再び2000年ごろから生産量が増加し、注目を集めています。海外の紅茶とはまた異なる魅力を持ち、近年生産者の増加とともに国内外での人気が高まってきました。
和紅茶は、地域ごとの風味の違いも楽しめるため、お気に入りの和紅茶を見つけて味わっていきたいものですね。