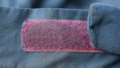「駅伝」は、お正月や秋の風物詩として親しまれ、選手たちが全力で走り、たすきをつなぐ姿は、多くの人々の心を動かすドラマがありますよね。
その駅伝は、日本で誕生した競技だとご存じでしたか? 背景や文化的な意味を知ると、観戦の楽しみも一層深まるのではないでしょうか。
今回は、駅伝の正式名称や成り立ち、たすきの意味、リレー走との違いや観戦の魅力、おもな開催日程・開催地まで、詳しくご紹介しております。
駅伝とは何?

駅伝の正式名称と基本ルール・競技形式
駅伝の正式名称は「駅伝徒競走(えきでんときょうそう)」です。
複数の走者が区間ごとに走り、次の走者へ「たすき」を渡してゴールを目指します。
陸上競技の一種であり長距離走にも含まれる競技で、コースや距離・区間数は各大会によって異なる点が特徴です。
スタートからゴールまでの流れ
スタート地点から第一区の走者が走り、区間ごとに待機している次の走者へたすきを渡します。
すべての区間を走り終えた時点でゴールとなります。途中でたすきが落下しても拾って再度つなぐことが可能ですが、たすきを渡せなかった場合は失格となります。
区間と距離の設定
大会ごとに距離設定は異なります。
例えば「箱根駅伝」では往路・復路合わせて10区間、総距離217.1kmです。
女子駅伝や高校駅伝では短めの距離に設定されており、参加選手の層や大会趣旨に合わせた調整が行われています。
駅伝競走の構成
駅伝は主に道路を使用する「ロードレース型」が一般的です。
都市部や自然の中を走るため、選手の走りだけでなく景観も楽しめます。テレビ中継では地域の名所が映されることもあり、観光的な側面も魅力のひとつです。
たすきをつなぐ意味と役割
駅伝の象徴である「たすき」には、単なる道具を超えた意味があります。
仲間の想いを次の走者へ託す証であり、途中で苦戦してもたすきをつなぐこと自体に大きな意義があるといえるでしょう。チームの努力と団結を体現する存在として、駅伝文化の中心に位置づけられています。
さらに、たすきは実用面でも重要な役割を担っています。
長距離を走る駅伝では、リレーのように小さなバトンを手に持ちながら走ると腕の振りや走行フォームに支障をきたす可能性があります。その点、肩から斜めにかけるたすきは両手を自由に使えるため、自然なフォームで走ることができ、長距離走に適した形といえます。軽量かつ丈夫に作られていることも、選手が集中して走り続けられる理由のひとつです。
このように、たすきは「仲間の心をつなぐ象徴」と「走るための合理的な工夫」の両方を兼ね備えた存在であり、駅伝を駅伝たらしめている不可欠な要素といえます。
駅伝の歴史について

日本の駅伝の由来・起源は
「駅伝」という言葉は、奈良時代から続いた「駅伝制(えきでんせい)」に由来します。
駅伝制は、馬を用いた「駅馬(えきば)」や「伝馬(てんま)」の制度で、飛脚などとともに急を要する文書や物資を、中継所でリレー式に伝達する仕組みでした。
宿場ごとに人馬を配置し、10km程度で交代しながら情報を運んだことが現代の駅伝につながったとされています。
歴史的な最初の駅伝
1917年(大正6年)に京都・三条大橋から東京・上野不忍池までの約508kmを23区間でつなぐ「東海道駅伝徒歩競走」が開催されました。
これは明治天皇の東京遷都50年を記念した博覧会の一環で、大日本体育協会の武田千代三郎が企画し、「駅伝」という名称を初めて用いました。
金栗四三の活躍
日本人で初めてオリンピックに出場したマラソン選手・金栗四三(1891~1983年)は、この大会で関東組のアンカーを務めました。
金栗は日本の長距離界の先駆者であり、駅伝文化の普及に大きな役割を果たしました。
箱根駅伝のはじまり
1920年に始まった「東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)」は、関東の大学が参加する学生駅伝です。
10区間・総距離217.1kmを往復する過酷なコースは、走力だけでなく精神力も試される舞台として知られています。新年の恒例行事として定着したといってよいでしょう。
さらに、箱根駅伝には地域振興や観光誘致の目的も背景にありました。
前年に実施された「東京奠都記念東海道駅伝」が大変好評だったことを受け、大学対抗の長距離駅伝として企画されたのです。当時、箱根の温泉街は冬期に観光客が減少する「閑散期」にあたり、正月に駅伝を開催することで旅館街や温泉地に人を呼び込む狙いもありました。
こうした背景があったため、単なる学生スポーツの枠を超え、地域と密接に結びついた文化的な行事として定着していったのです。
なぜ箱根駅伝は正月に行われる?
箱根駅伝が正月に開催される理由は、学生が冬休みで参加しやすかったことや、交通量が比較的少ない時期だったことにあります。
高度経済成長期には交通事情の影響もあり、正月開催が最も適していると判断された結果、現在の形に定着したといわれています。
実業団駅伝とその影響
社会人選手が出場する「ニューイヤー駅伝」も注目度が高い大会です。企業チームが地域や社風を背負って戦う姿は、地域社会や企業文化とも結びつき、選手育成の場としても重要な役割を果たしています。
実業団駅伝が登場するようになったのは、1950年代です。
復興期、日本の産業とともに企業のスポーツ振興が進み、企業が職場活動の一環として陸上競技・駅伝を支援するようになりました。特に、企業チームの間で長距離競走での対抗が関心を集め、「会社という組織で実績を競う場」が求められていたことが、実業団駅伝の誕生につながりました。
最初の実業団駅伝大会は 第1回 全日本実業団対抗駅伝競走大会 で、1957年3月3日に三重県で行われました。この大会には企業チーム14チームが参加し、距離は当時約83.5km、優勝は八幡製鐵でした。
また、この大会はその後、「元日開催」が定着するまでいくつか試行があり、1988年の第32回大会から元日の1月1日開催が正式に定まり、「ニューイヤー駅伝」の通称が広く使われるようになりました。
駅伝文化としての人気
「個人の走力」と「チームの絆」の両面が問われる競技性が、多くの人に共感を呼び、駅伝は日本独自のスポーツ文化として広がりました。たすきが象徴する連帯感が、人々を惹きつけ続けています。
駅伝大会の種類

主な国内開催駅伝には何がある?
代表的な駅伝には「箱根駅伝」「ニューイヤー駅伝」「全日本大学駅伝」「全国高校駅伝」「全国女子駅伝」などがあります。
さらに地域ごとにも特色ある大会が存在し、地域の風物詩として親しまれています。
三大駅伝とは
大学生の「出雲駅伝」「全日本大学駅伝」「箱根駅伝」を「学生三大駅伝」と呼びます。それぞれ距離やコースが異なり、総合力を競う重要な舞台です。
- 出雲駅伝:毎年10月、島根県の出雲大社前をスタートし、出雲ドーム前がゴール。6区間・45.1kmで争われます。シーズン最初の全国規模の大学駅伝です。
- 全日本大学駅伝:毎年11月、名古屋・熱田神宮西門前から三重・伊勢神宮内宮宇治橋前までを走破。8区間・106.8kmで行われ、大学駅伝日本一を決める大会です。
- 箱根駅伝:毎年1月2日・3日、東京・大手町をスタートし箱根・芦ノ湖を折り返す往復コース。10区間・217.1kmという長大な距離を走る学生駅伝の最高峰であり、全国的に注目されます。
全国大会と地方大会の特性
全国大会は大規模な中継で注目を集める一方、地方大会は地域密着型で運営されます。地域住民が参加し、地元の特色を活かしたコースが設定される点も見どころです。
地域大会の開催日程などは、各運営サイトを確認なさってくださいね。
日本陸上競技連盟公式サイト
大会のルールや最新情報は日本陸上競技連盟(JAAF)の公式サイトで公開されています。
正確な情報を知りたい場合は、公式発表を確認しましょう。
2026年主な駅伝開催日程および開催地一覧
※日本陸上競技連盟(JAAF)公式サイトおよび地域大会検索で確認できた内容のみ一覧表でお示ししております。小規模の地域駅伝大会など、把握しきれていない場合がありますので、詳細は各自ご確認のほど、お願いいたします。
| 月 | 駅伝大会等 | 開催地/距離・区間数 |
| 1月 | 第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝) | 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖往復
217.1km/10区間(往路107.5km・復路109.6km) |
| 第70回全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝) | 群馬県(前橋市発着)
100km/7区間 |
|
| 皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | 京都市(西京極陸上競技場発着)
42.195km/9区間 |
|
| 天皇盃 第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 | 広島市(平和記念公園前発着)
48km/7区間 |
|
| 5月 | 企業対抗駅伝2026 東京大会 | 東京・お台場
25km/5km×5区間 |
| 企業対抗駅伝2026大阪大会 | 大阪・淀川河川公園
25km/5km×5区間 |
|
| ノーザンホースパーク駅伝2026 | 北海道・千歳市
16km/2km×8区間 |
|
| 佐鳴湖国際駅伝大会 | 静岡・浜松市
約42.195km/14区間 |
|
| ふれあい赤羽駅伝 | 東京・赤羽
ハーフマラソン距離(21.0975km)を4人で分担 |
|
| 10月 | 第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 島根・出雲大社〜出雲ドーム
45.1km/6区間 |
| 第44回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 宮城・仙台市(弘進ゴムアスリートパーク発〜仙台市陸上競技場着)
38.6km/6区間 |
|
| 11月 | 第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 愛知・名古屋(熱田神宮)〜三重・伊勢市(伊勢神宮内宮宇治橋前)
106.8km/8区間 |
| 第46回全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝) | 宮城・仙台市
42.195km/6区間 |
|
| 12月 | 第34回全国中学駅伝大会 | 滋賀・希望が丘文化公園陸上競技場
男子18km/6区間・女子12km/5区間 |
| 全国高等学校駅伝競走大会(男子第77回・女子第38回) | 京都市(西京極陸上競技場発着)
男子42.195km/7区間・女子21.0975km/5区間 |
|
| 2026全日本大学女子選抜駅伝(富士山女子駅伝) | 静岡・富士宮市〜富士市
43.4km/7区間 |
駅伝とリレーの違い

はじめに、両者の共通点と違いをまとめた一覧表からご覧ください。そのあと細目をご紹介しております。
駅伝とリレー走の共通点と違い一覧表
| 駅伝 | リレー走 | |
| 共通点 | 仲間と複数区間ををつなぎ、団体で順位やタイムを競う | 仲間と複数区間をつなぎ、団体で順位やタイムを競う |
| 繋ぐ | たすき | バトン |
| 走る距離 | 長距離(マラソンに近い距離を分担)で長短不定 | 短距離〜中距離が中心で一定 |
| 走る場所 | 公道・ロードコース(坂道や地形の変化あり) | 競技場トラック(環境の変化は少ない) |
| 区間の特徴 | 区間ごとに距離・地形が異なる(上り坂・下り坂・平地など) | 全員が同じ距離・同じ条件で走る |
| 戦略性 | 選手の得意分野に合わせた区間配置が重要 | スピードを落とさず正確にバトンをつなぐ技術が重要 |
共通点:長距離走ジャンル・複数人が繋ぐ団体競技
駅伝もリレーも、「複数の人がバトンまたはたすきをつなぎながら順位やタイムを競う団体競技」である点では共通しています。
駅伝は「長距離競走(ロードレース/長距離走)」の範疇にあり、一人でフルマラソンやハーフマラソンを走るのと同じように、持久力・ペース配分・体力の配分などが求められます。
また、リレー走でも中距離種目になると速さと持久力のバランスが重要になります。
違い:競技形式・戦略性・バトンかたすきか
両者の競技形式には、距離・区間数・コースの環境などに大きな差があります。
- リレー走は、競技場内のトラック内を使い、各人が一定の距離で短距離または中距離を複数人でつなぐ形式です。
- 一方で駅伝は、開催地ごとに異なる公道や道路を使い、各区間ごとに柔軟性を持たせた距離で長距離を複数人でつなぐ形式です。
また、リレーでは「バトン」を手で受け渡しますが、駅伝では「たすき」を肩にかけて渡します。この違いが駅伝の象徴性を高めています。
駅伝区間の多様性・地形・戦略性
- 区間ごとの距離・地形の変化: 駅伝では、上り坂・下り坂・平坦な道など、地形の違いが区間ごとに存在することが多くあります。こうした特性を活かすため、各大学・チームは区間ごとに得意な選手を配置する戦略を立てます。 リレー走では、トラックで同じラップを走ることが多いため、地形の違いや景観の変化という環境的要素はほぼありません。
- 走者の走る距離の個人差: 駅伝では区間ごとに距離が異なることが多く、ある区間は長く、ある区間は短く設定されている大会もあります。 リレー走では、通常全ての走者が同じ距離を走るのが基本です。
- 環境・気象の影響の程度: 駅伝は公道を使うため、風・気温・湿度・道路の傾斜など自然要素の影響を受けやすいです。 リレー走は競技場トラックで行われるため、環境の変動が小さく、公平性の管理もしやすいです。
駅伝の魅力

スポーツとしての見どころ
個人の走力だけでなく、区間配置や采配などチーム全体の戦略が結果を左右します。区間賞をめぐる戦い、ドラマチックな逆転劇など、駅伝ならではの展開があります。
応援の楽しさ
沿道で声援を送る観客の存在も駅伝の重要な要素です。地域住民が旗を振り、拍手を送り、選手を励ます姿は駅伝文化の一部となっています。
記録と名選手の誕生
選手やチームの背景やストーリーを知ることで、観戦が一層楽しめます。メディアの特集やドキュメンタリーも視聴者の共感を呼んでいます。
駅伝では歴史的な名勝負が数多くあり、そこから日本を代表する長距離ランナーが誕生してきました。駅伝はマラソン界への登竜門としても位置づけられています。
特に箱根駅伝では、5区の山上りで圧倒的な走りを見せた選手が「山の神」と呼ばれて語り継がれています。初代は順天堂大学の今井正人選手(2005〜2007年連続区間賞)、2代目は東洋大学の柏原竜二選手(2009〜2012年4年連続区間賞)、3代目は同じく東洋大学の神野大地選手(2014〜2015年)です。彼らの走りは駅伝ファンの記憶に強く残り、後にマラソンや実業団でも活躍しました。
このように駅伝は、記録更新や名勝負だけでなく、特定の区間からスターが生まれる舞台でもあり、その存在が大会をさらに魅力的なものにしています。
地域貢献とチームワーク
駅伝は地域社会に根づいた競技でもあります。企業や学校が参加することで地域振興につながり、たすきが象徴するチームワークが多くの若者に影響を与えています。
また、監督、コーチ、マネージャー、医療スタッフ、ボランティアなど、多くの人々が大会を支えています。選手だけでなく裏方の存在を知ることで、駅伝の奥深さを実感できます。
国際的な影響と海外駅伝の特徴
近年ではフランスやチェコ、アメリカ、中国などでも駅伝形式の大会が行われています。
ただし日本ほど広範には根づいておらず、独自の展開を見せるものの、「EKIDEN」という言葉は国際的にも通じるようになってきました。
駅伝の観戦ガイド

観戦の楽しみ方
テレビ観戦では解説やタイム差の表示が分かりやすく、走者の表情や戦況をじっくり追うことができます。
現地観戦では、沿道で選手が目の前を駆け抜ける迫力や、周囲の観客と一体になって応援する臨場感が魅力です。それぞれの楽しみ方があり、両方を組み合わせるとより奥深く楽しめます。
大会のスケジュールとコースの把握
事前に公式サイトなどでスケジュールやコースを確認しておくことで、観戦体験が充実します。
応援場所を決める際には交通アクセスのしやすさや、混雑具合も考慮して準備しておくとよいでしょう。また、人気の区間や中継所は人が集まりやすいため、早めに移動して場所を確保する工夫も必要です。
応援の方法と観客の役割
拍手や旗を振る応援は選手の力になります。声援を送る際には大会のルールや周囲の観客に配慮しながら、選手を後押しすることが求められます。
観客の存在そのものが駅伝の雰囲気を作り出しており、沿道での温かい応援は大会を盛り上げる大きな要素です。
まとめ

- 駅伝は日本発祥の競技で、古代の駅伝制や飛脚制度がルーツとなっている。
- 正式名称は「駅伝徒競走」であり、複数人がたすきをつなぎながら長距離を走る団体競技。
- たすきは仲間の想いをつなぐ象徴であり、肩からかける形は長距離走に適した実用性も備えている。
- 箱根駅伝は東京奠都駅伝の成功と箱根温泉街の観光誘致を背景に誕生し、現在では新年の国民的行事となっている。
- 実業団駅伝は1957年に始まり、現在は「ニューイヤー駅伝」として元日の恒例行事に定着。企業文化や地域社会とも結びついている。
- 駅伝とリレーはともに「つなぐ」競技だが、距離・コース・バトンやたすきの違いが大きなポイント。駅伝は区間ごとの地形や距離の違いが戦略性を生む。
- 駅伝からは「山の神」に代表されるようにスター選手が誕生し、マラソン界へ羽ばたくケースも多い。
- 観戦はテレビと現地の両方に魅力があり、沿道での応援は選手の力となり、大会全体を盛り上げる。
- 2025年には全国規模から地域型まで数多くの駅伝が開催され、大学・実業団・高校・中学・市民レベルと幅広い層で親しまれている。
駅伝について知ることで、単なるスポーツとしてだけでなく、日本の歴史や地域文化、そして人々の思いをつなぐ象徴としての側面を理解するにつながるのではないでしょうか。
選手たちがたすきに託すものは記録だけでなく、仲間や地域、未来へと続く大切な物語でもあるのです。
これらの想いやストーリーを感じながら、観戦・応援する楽しみが広がりますように。