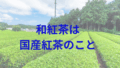甘味にほっとする「おしるこ」と「ぜんざい」、どちらも小豆とお餅から作られますが、その違いをよく知らずに食べていました。
素朴な疑問から、由来や歴史、関東・関西での呼び方と特徴による違いとともに、ご当地ものやご家庭でのちょい足しアレンジによる楽しみ方もご紹介いたします。
知ればシンプルかつ奥深い両者、あなたは今日、どちらにしましょうか?
おしることぜんざいの基本を知ろう
おしることは?由来・歴史や特徴

「おしるこ」は、煮た小豆をこしたり、つぶしたりして作る甘い汁もので、こしあんを使ったものが多く、さらりとした口あたりと上品な甘さが特徴です。
その由来にはいくつかの説がありますが、江戸時代に餡(あん)の汁の中に実(子)として餅を入れた「餡汁子餅(あんしるこもち)」が転じて、汁粉(しるこ)になったといわれています。
その際用いられた、小豆を乾燥させて粉末にしたさらしあんを水で溶いた「小豆汁(あずきじる)」から、汁と粉でお汁粉と呼ばれるようになったそうです。
この小豆汁に団子を煮込んだ「すすり団子」も登場しますが、砂糖がまだ高価だった当時は、塩味に仕立てた汁物としての性格が強かったようで、上から砂糖をふりかけて食べていたと伝えられます。
やがて時代とともに砂糖が一般に流通するようになると、現在のような甘いおしるこが一般に広まりました。
現在では、最中に入ってお湯を注ぐだけのインスタントやレトルト、缶入りなどさまざまなおしるこが市販され、甘味処などでの提供なども含め、より手軽に食べられるようになりましたね。
また、おしるこの原型はさらに古く、中国から伝わった穀類の粥文化が伝わったことに由来するといわれ、平安時代の宮中では、もち米に塩を加えて煮つめて甘くした糖粥が食べられており、それに甘味を加えたものが後のおしるこの元と考えられています。
ぜんざいとは?由来二説や歴史と特徴

「ぜんざい」は、一般的に小豆を炊き、砂糖を加えて煮込んだ粒あんを使い、もちや白玉を加えたもので、小豆を潰さず形が残ることによる豊かな風味と食べ応えが大きな特徴です。
「ぜんざい」という言葉には、いくつかの由来が伝わっています。
ひとつは、出雲地方の神在祭(かみありさい)でふるまわれた「神在(じんざい)餅」が訛って「ぜんざい」になったとされ、出雲では今でも神在祭に「ぜんざい」を供える習慣が残っています。
もうひとつは、仏教用語の「善哉(ぜんざい)」に由来する説で、「善哉」には、よきかな・なんとめでたいことかという意味を持ち、室町時代の禅僧(一休禅師といわれています)が、小豆を煮た甘い料理を口にした際、「善哉、善哉」と称賛したことから、この名が定着したといわれています。
いずれの説にしても、「ぜんざい」は祝いごとや感謝の気持ちを込めて振る舞われてきた料理といえるでしょう。古くから小豆は邪気を祓うとされ、ハレの日の食材として用いられてきました。
ぜんざいもそうした意味合いを持つ、縁起のよい甘味なのです。
ぜんざい・おしるこの日(10/31や2/8)
・10月31日は「出雲ぜんざいの日」として、2007年に島根県出雲市の「出雲ぜんざい学会」によって制定されました。
1031の日付を「ぜん(千)ざ(3)い(1)」とする語呂合わせにより、神在(じんざい)餅からぜんざいとなった伝承を元に、広く親しんでもらえるようにとの趣旨があるそうです。
・2月8日は「ぜんざい・おしるこの日」として、2025年2月に三重県の井村屋グループ会社によって制定されました。
古くから日本に伝わる事八日(2月8日もしくは12月8日)は、小豆を使った「お事汁(おことじる)」を食べて無病息災を祈る日とされており、また10月31日の出雲ぜんざいの日から約465(しるこ)日後となることが多いため、この日にぜんざいもおしるこもどちらも楽しんでもらえるようにとの趣旨だそうです。
おしることぜんざいの違いは?

一般的な観点で大きく分けると、「おしるこ」は(粒あんや)こしあんを水でのばし滑らかにしたもの、「ぜんざい」は小豆の粒を残して煮たものという違いがあるといえるのですが、実際の区別はもっと複雑なものでした。
以下の観点から、みていきましょう。
関西・関東による呼び方の違い
「おしるこ」と「ぜんざい」は、地域によって呼び方が入れ替わることもあります。
関東では、汁気のあるものを「おしるこ」、汁気の少ないものを「ぜんざい」と呼びます。
一方、関西では、粒あんを使ったものを「ぜんざい」、こしあんを使った汁ものを「おしるこ」と区別する傾向があります。
つまり、東西で基準が異なるのです。
こしあんとつぶあんの違い
おしるこ・ぜんざいの違いを語るうえで欠かせないのが、あんこの種類です。
こしあんは、小豆を煮て皮を取り除き、なめらかに裏ごししたもので、舌触りがなめらかで上品な甘さが特徴です。
一方、つぶあんは小豆の形を残し、ほくほくとした食感が魅力。素材の風味をより強く感じられる点が人気です。
汁気の違い
おしるこは汁の割合が多く、さらっとした飲み口が魅力で、一方のぜんざいは煮詰めることでとろみが出て、豆の旨みと甘みが濃く感じられます。
どちらもお餅や白玉との相性が良く、お正月の時期の一品や冬場のほか、冷やして夏場にも通年の甘味として楽しまれています。
地域ごとの違いを探る

「ぜんざい」と「おしるこ」は、各地域により特徴や定義となる基準が異なります。日本の食文化の多様性の面白さや楽しさの一端が伺えるものといえますね。
関東のぜんざいとおしるこ・種類
関東では、田舎しるこや小倉しるこなど、汁気の多いものが「おしるこ」、汁気のないものが「ぜんざい」と区別し、粒あんかこしあんかでは区別していない場合が多くみられます。
一部では、こしあんを用いるものは上品な見た目から「御前しるこ」、つぶあんのものを「田舎しるこ」と区別している場合もあります。
関西のぜんざいとおしるこ・別名
関西では、粒あんを煮た汁ものを「ぜんざい」、こしあんを溶かした汁ものを「おしるこ」と呼ぶ傾向にあります。
また、汁気のないものには「亀山」「金時」といった別名のものもあります。
亀山は、丹波大納言小豆の産地で、じっくり炊いて水分のない粒あんとお餅をいただく別物といえる一品です。
金時は、金時小豆と呼ばれる赤くて大きな品種に対してもしくは、赤色を金時色と称したことから、宇治金時などかき氷にのせた甘く煮た小豆のことを指し、こちらも別物を指します。
京都や大阪では、濃厚な甘味と焼き餅の香ばしさを楽しむスタイルが定番です。
九州や北海道の呼び方と特徴

九州では、基本的に関西と同じく、粒あんを使ったものを「ぜんざい」と呼ぶ傾向があります。
また一部の地域では、お餅が入っているものを「おしるこ」、白玉団子が入っているものを「ぜんざい」と分けるところもあり、呼び方や食べ方に地域差が見られます。
冬の行事やお祝いの場などでふるまわれることも多く、身近な甘味として親しまれています。
一方、北海道では「おしるこ」と「ぜんざい」が明確に区別されていないことが多く、どちらの名称も使われています。
かつて北海道では、寒冷な気候のためにもち米などの作物が育ちにくく、餅や白玉を入れる食べ方は一般的ではなく、代わりに、カボチャやジャガイモを加えた「いもぜんざい」「かぼちゃぜんざい」のような郷土的なアレンジが生まれ、家庭の味として受け継がれてきました。
各地域別おもな違い区分一覧表
| 地域 | 粒あん(汁あり) | こしあん(汁あり) | 汁気なし |
| 関東 | おしるこ(田舎汁粉・小倉汁粉) | おしるこ(御膳汁粉) | ぜんざい |
| 関西 | ぜんざい | おしるこ(御膳汁粉) | 亀山 |
| 九州 | (関西と同様)ぜんざい
※一部地域では白玉入り=ぜんざい |
おしるこ
餅入り=おしるこ |
※北海道では、おしるこ・ぜんざいの名称は明確に区別されていないことが多い
多様性!ご当地ぜんざい色々
他にもあるかもしれませんが、有名どころをご紹介いたします。ご当地に立ち寄った際には、いただいてみたいものですね。
・三重県・伊勢名物「赤福ぜんざい」:赤福餅を温かい小豆汁に入れた逸品。伊勢神宮参拝の楽しみのひとつとして人気。
・大阪府・法善寺横丁「夫婦善哉(めおとぜんざい)」:織田作之助の小説でも知られ、二つの器に分けて提供される縁起のよい甘味。
・島根県・出雲ぜんざい:神在祭に由来し、「神在(じんざい)」がなまって「ぜんざい」と呼ばれるようになったルーツとされています。紅白餅が入るのが特徴。
・福岡県・川端ぜんざい:昔ながらの濃厚な甘味で知られ、観光客にも人気。
・沖縄ぜんざい:金時豆を黒糖で煮て、その上にかき氷をのせる夏の定番スイーツ。冷たい「ぜんざい」は沖縄独自の文化です。
おしるこ・ぜんざい家庭での作り方

おしるこの基本的な作り方
材料は小豆・砂糖・餅とシンプルで、小豆をやわらかく煮て、裏ごししてから砂糖を加えて仕上げます。市販のこしあんを使うとより手軽に。焼き餅を加えると香ばしさが増し、白玉を入れるとやさしい口あたりになります。
材料(2人分)
- 小豆(乾燥)……100g
- 水……約600ml(煮る用)+適量(ゆでこぼし用)
- 砂糖……60〜80g(好みの甘さで調整)
- 塩……ひとつまみ
- 餅(切り餅)……2〜4個(お好みで)
作り方
- 下準備
小豆をさっと洗い、たっぷりの水に一晩(6〜8時間ほど)浸します。
時間がない場合は、沸騰したお湯を注いで1〜2時間おく「早戻し法」でも可能で。 - ゆでこぼしで渋みを取る
鍋に小豆とたっぷりの水を入れて火にかけ、沸騰したら弱火で5分ほど煮て火を止めます。
湯を捨てて軽く水洗いします。これで渋みが抜け、豆の風味がやさしくなります。 - 本煮
鍋に小豆と約600mlの水を入れ、弱火で1時間ほどじっくり煮ます。
途中で水が減ったら差し水をしながら、焦げ付かないよう注意します。
豆が指でつぶれるくらいになったら火を止めます。 - あんを仕上げる
豆を軽くつぶすか裏ごししてこしあんにし、砂糖を2〜3回に分けて加えます。
砂糖は一度に加えず、豆が十分やわらかくなってから。
味を見ながら塩をひとつまみ入れ、甘味を引き立てます。 - 仕上げ
餅を焼いて器に入れ、温めたおしるこを注ぎます。
ポイント
- 圧力鍋を使う場合は加熱時間を短縮でき、約15分でやわらかく煮えます。
- 砂糖は三温糖ならまろやかに、白砂糖ならすっきり仕上がります。
- 豆の形を残したい場合は、こさずにつぶあん風に仕上げてもOKです。
羊羹・あずきバーからレンジでおしるこ

市販の羊羹やあずきバーを活用すれば、短時間でおしるこが完成します。
小鍋や電子レンジで温め、少量の水を加えて溶かすだけで、餅や白玉を添えれば即席甘味の出来上がります。
・ミニ羊羹の場合
耐熱容器に、58g位のミニ羊羹1本と80~100mlの水を入れ、ラップをせず電子レンジで500w3~5分加熱し、スプーンで溶かして完成です。
・あずきバーの場合
マグカップなど深さのある耐熱容器に棒の刺さったまま2本入れて、電子レンジ600wで3分、500wなら4分程度加熱し溶けたら完成です。
また、別容器にお餅とかぶる程度の水を入れて同様に電子レンジで加熱して、おしるこにくわえると手軽にもちもち食感でいただけますよ。
ぜんざいの基本的な作り方
ぜんざいは、小豆をゆでこぼしてから弱火でじっくり煮るのがポイントで、煮汁を残すかどうかで食感が変わります。缶詰のゆであずきを使う場合は、少し煮詰めて水分を飛ばすと手軽に家庭風ぜんざいが完成します。
材料(2人分)
- 小豆(乾燥)……100g
- 水……約600〜700ml(煮る用)+適量(ゆでこぼし用)
- 砂糖……70〜90g(甘さはお好みで)
- 塩……ひとつまみ
- 餅(切り餅)……2〜4個(焼き餅・煮餅どちらでも)
作り方
- 下準備
乾燥小豆をさっと洗い、たっぷりの水で煮立てます。
沸騰したら弱火で5分ほど煮てからお湯を捨て、「ゆでこぼし」で渋みを取ります。 - 本煮
新しい水(約600〜700ml)を加え、弱火で1時間ほどじっくり煮ます。
途中で水が減ったら差し水をし、豆が指で軽くつぶれるくらいのやわらかさになったらOKです。 - 味つけ
砂糖を3回ほどに分けて加え、溶かしながら煮詰めます。
一度に入れると豆が固くなりやすいので、焦らず少しずつ加えましょう。
仕上げに塩をひとつまみ入れて味を引き締めます。 - 煮詰め方で変わる食感
・煮汁を多めに残す →「汁ぜんざい」風(さらりとした口当たり)
・しっかり煮詰める →「亀山」風(濃厚で豆の旨みが際立つ) - 仕上げと盛りつけ
焼いた餅を器に入れ、温かいぜんざいをたっぷり注ぎます。
ポイント
- 豆の香りを活かすなら、焦げ付かないよう弱火をキープ。
- 三温糖を使うと深みのある味に、黒糖を使うとコクが出ます。
- 圧力鍋を使用する場合は、粒がつぶれ過ぎないよう圧力をかける時間を短めにし、開けたあと確認しながら追加して弱火で煮るとうまくいきます。
白玉団子の簡単レシピ
材料(2人分)
- 白玉粉……100g
- 水……約90ml(様子を見ながら調整)
白玉粉に水を少しずつ加えて耳たぶ程度のやわらかさに練り、生地を直径2cmほどの大きさに丸めると、大きさをそろい火の通りが均一になります。沸騰したお湯でゆで、浮き上がったら冷水に取って出来上がりです。
もちもちの白玉は、おしるこやぜんざいのトッピングにぴったりですね。
ちょい足しアレンジ・相性のよい食べ合わせ

余ったら簡単ちょい足しアレンジ
残ったおしるこやぜんざいは、少し工夫するだけで別のデザートに変身します。ほんの一例ですが、おすすめのちょい足しアイデアです。
- 牛乳や豆乳を加えてまろやかに
- ココアや抹茶を混ぜて風味を変化
- ココナッツミルクで南国風に
- 甘酒をプラスしてやさしい味わいに
- きな粉やすりごまで香ばしさをアップ
- カボチャやさつまいもを加えて彩り豊かに
- アイスをのせて温冷スイーツに
- 寒天やゼリーで固めて水ようかんに
- 餅のほかにオートミールやグラノーラを添えて粟ぜんざいの応用
他にもおいしくなるちょい足しを、色々お試しくださいね。
塩味との相性のよさを活かした食べ合わせ
小豆の甘さを引き立てるのが、塩気のある食材です。
一緒に食べ合わせることで全体の味わいが締まり、甘みに奥行きのある風味が生まれます。
おすすめの食べ合わせ例
- 焼き餅に塩をひとふり:香ばしさと甘味のバランスが絶妙に。
- 塩昆布を添える:関西では定番の食べ方で、甘じょっぱい組み合わせが人気。
- 梅干し・塩豆・シソの実の佃煮を添える:少量で甘味に深みが出て、新鮮な味わいに。
- 味噌+粒あんのアレンジ:
小鍋に少量の白味噌(小さじ1/2ほど)を溶いた湯を用意し、そこに粒あんをお好みの分量加えて混ぜます。
軽く温めてから焼き餅を入れると、味噌の香ばしさとあんこの甘味が調和し、まろやかな“和風デザートスープ”のような味わいに。 - 醤油を塗って炙った焼き餅を添える:香ばしい香りが加わり、甘味が一層引き立ちます。
また、煎茶の渋みやほうじ茶の香ばしさとも相性抜群で、おいしくいただけますよ。
まとめ

「おしるこ」と「ぜんざい」は、一般的な観点で大きく分けると、以下のような違いがあります。
- 「おしるこ」は(粒あんや)こしあんを水でのばし滑らかにしたもの
- 「ぜんざい」は小豆の粒を残して煮たもの
さらに、歴史や地域による定義の違いやご当地ぜんざいなど、より深く豊かな甘味文化をもっていました。各地域による違いの一覧表を再掲いたします。
| 地域 | 粒あん(汁あり) | こしあん(汁あり) | 汁気なし |
| 関東 | おしるこ(田舎汁粉・小倉汁粉) | おしるこ(御膳汁粉) | ぜんざい |
| 関西 | ぜんざい | おしるこ(御膳汁粉) | 亀山 |
| 九州 | (関西と同様)ぜんざい
※一部地域では白玉入り=ぜんざい |
おしるこ
餅入り=おしるこ |
今では全国的に普及し、自販機で「缶入りしるこ」を見かけるのも、冬の風物詩といえるのではないでしょうか。
ご家庭でも基本の作り方のほか、市販品やちょい足しアレンジ次第で季節を問わず楽しめます。
また、ぜんざい・おしるこにゆかりのある2月8日および10月31日には、その歴史や由来に思いを馳せつつ、甘味処を見かけた際には、ぜひその土地やお店ならではの味を楽しんでみるというのも、ステキなことではないでしょうか。