絹豆腐はその滑らかな食感が特徴ですが、冷凍するとどのように変わると思いますか?
そもそも豆腐は冷凍していいのか、解凍後の変化を含め、メリットや活用法があるのかなど、気になることを調べまとめてみました。
今回は、冷凍・解凍の仕方や、解凍後の食感変化を活かした調理アイデアおよびレシピも3つ、ご紹介しております。手軽に食べられる豆腐、日常に取り入れる機会を増やしてみませんか。
絹豆腐を冷凍するとどうなるの?

豆腐は、冷蔵保存するのが一般的ですが、まずは、冷凍した後どうなるのかを知っておきましょう。
冷凍するメリットとデメリット
メリットや魅力
絹豆腐を冷凍することで得られるメリットには、以下のような点があります。
- 一時的な冷凍が可能:結論として冷凍も可能なのです。
- 水分が抜けて凝縮される:冷凍すると水分が抜け、豆腐自体が凝縮されるため、濃厚な味わいになります。
- 味が染み込みやすくなる:冷凍解凍によってスポンジ状や層状になり、煮汁や調味料が染み込みやすくなるため、煮物や炒め物に向いています。
- 独特の食感を活かす活用法:あえて冷凍し、解凍後の水分が抜けた豆腐の食感を、肉や大豆ミートの代わりとして利用する方法もあります。
デメリット
一方で、冷凍保存にはデメリットもあります。
- 冷奴には不向き:解凍後は滑らかさが失われ、ボソボソとした食感になるため、そのまま食べる冷奴には適しません。
- 水分が抜け柔らかさは減る:スポンジ状になることで、水っぽさが抜けてしまい、柔らかさは減少します。
- 風味が変わる:冷凍によって豆腐自体の特有の風味はやや薄れるため、シンプルな料理には不向きな場合があります(不足分の風味を補う必要があります)。
冷凍可能な豆腐の種類は
豆腐の種類によって冷凍・解凍後の仕上がりが異なりますが、
基本的には、絹豆腐・木綿豆腐・充填豆腐・焼き豆腐のいずれも、冷凍が可能です。
冷凍豆腐の食感変化と仕組み

冷凍すると豆腐内部の水分が氷の結晶となり、解凍後には水分が抜けて、スポンジ状や層状の状態になります。
豆腐の銘柄によってもそれぞれ異なりますが、主に以下のように変化する場合が多く、それにより調味料がしっかり染み込む特徴が生まれます。
- 絹豆腐や充填豆腐:層状に変化し、湯葉のような食感に(見づらいですが、上の写真は絹豆腐を冷凍・解凍した断面で、層状になっています)
- 木綿豆腐や焼き豆腐:スポンジ状に変化し、柔らかめの高野豆腐や大豆ミートの塊のような食感に
冷蔵保存との違い
冷蔵保存では豆腐の滑らかさや風味を維持できますが、充填豆腐以外は、保存期間は数日と短い場合がほとんどです。
一方、冷凍後は独特の食感を活かした料理に使えるという利点があります。
冷奴やサラダなど滑らかな状態で食べる場合と使い分けることで、日々の暮らしに豆腐を取り入れやすくなるのではないでしょうか。
冷凍方法4つと留意点

急いでいる時は、パックをそのまま冷凍できるため便利ですが、さらに、解凍後の用途に応じた冷凍方法にしておくと重宝します。
パックのまま、水切り後そのまま、カットして、つぶしてからと、4つの方法をご案内していきます。
パックのまま冷凍
最も簡単な方法です。
豆腐をパックごと冷凍する際は、容器内でが水分が膨張し破けてしまう場合もありますので、念のため密閉袋に入れて水平な場所において冷凍するのがポイントです。
水切りして密閉容器で冷凍

パックから出して水を切った上で、サイズが合えばそのまま冷凍対応の密閉容器に入れて冷凍します。
容器の大きさが合わない場合などでは、水切りした豆腐をラップで包み、密閉袋に入れて冷凍します。
水入りの場合よりも短時間で冷凍することができます。
カットして密閉袋に入れて冷凍

水気を切った後、1丁を8~16等分など、解凍後に使いやすいサイズにカットし、さらにキッチンペーパーで水分と拭き取って、そのままもしくはラップで包んでから密閉袋に入れて冷凍します。
また、小さくカットしすぎると豆腐が崩れやすいため、バットの上にカット片が重ならないよう平らに広げて冷凍してから袋にいれると、ムラなく最も早く冷凍できます。
ラップに包んでから冷凍しておけば、解凍後の分割使用が楽になり、より便利ですよ。
少量だけ余った場合にも、同様に保存できます。
つぶしてから密閉袋で冷凍
特にひき肉代わりや白和えなどとして使う際に便利です。
袋の上から指で押して薄く広げるか、ブレンダーなどでペースト状などお好みの細かさまでのばしてから密閉袋に入れて凍らせ、分割用に筋目をつけておくと、必要分だけ折って使えます。
また、袋ごと解凍した後に端をカットして、フライパンや鍋などに直接絞り出して使うこともできます。
冷凍後も早めに消費
冷凍庫の開閉頻度などの影響も含め、さらに水分が失われ、風味や食感も落ちるため、早めに使い切りましょう。
食べ忘れてしまう場合に備え、日付を記載しておくとよいでしょう。
豆腐の解凍方法3つ

冷蔵庫、流水、電子レンジの3つの方法があり、いつ調理するのかに応じて使い分けできます。
くれぐれも常温による自然解凍、および解凍後の再冷凍は避けるよう、留意しましょう。
冷蔵庫内で解凍
冷蔵庫でじっくり解凍する方法は、最も手間いらずです。この時、解凍により容器などから水分が出るため、バットやキッチンペーパーの上に載せて庫内が水浸しになるのを防ぐのがポイントです。
解凍時間は6~8時間程度かかりますが、庫内の温度が一定であるため、豆腐が急激に変化することを防ぎます。解凍後に水切りを行うことで、さらに調理がしやすくなります。
流水による解凍
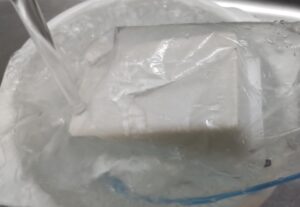
流水で解凍する場合、パックや袋ごと水に浸けるか、弱い流水に当てます。
解凍時間は20~30分と短時間で済みますが、ある程度解凍した後で電子レンジを併用するとさらに時短になります。
電子レンジでの解凍

急いで解凍したいときは、電子レンジが便利です。
・パックごと冷凍した場合には、そのままレンジ解凍することはできないため、冷蔵庫内や流水で取り出せる程度に解凍した後、豆腐を別容器に移し替えてからレンジを使用します。
ラップをかけて「解凍モード」または500wで2~4分程度加熱します。加熱しすぎると水分が飛び、さらに固くなるため、少しずつ様子を見ながら追加加熱して解凍するようにしましょう。
・カットして冷凍した場合は、量や厚さにもよりますが、500wで1~2分程度でその後様子を見ながら数十秒ずつ加熱するとよいでしょう。解凍モードを使う場合は、始めのうちはそばについて様子を見て、分量と加熱時間などに慣れていきましょう。
水分が抜けた豆腐の使い道
解凍後に水分が抜けてしっかりした食感になった豆腐は、煮物、炒め物、揚げ物、そぼろ風料理、さらには高野豆腐風の料理にも活用できます。
特に肉や大豆ミートの代わりとして使うことで、こってりした味付けでも軽い仕上がりになります。
次の章で具体的なアイデアやレシピについてご案内いたします。
解凍後の料理アイデアとレシピ3つ

煮物・鍋・揚げ物・炒め物やそぼろ料理など幅広く活用できる
冷凍豆腐は水分が抜けてスポンジ状もしくは層状になるため、煮汁や調味料が染み込みやすく、煮物や鍋、揚げ物、炒め物などに適しています。
また、崩れやすい性質を活かしてそぼろ風料理にも利用可能で、豆腐の形状を変えることで、万能に使用できる優れた食材です。
肉や大豆ミート代わりに

料理の種類に応じて豆腐の形状を工夫することでさまざまな豆腐料理の食べ応えをアップできる他、肉のような食感を再現し代用することが可能です。
- 解凍した豆腐をある程度カットした後、さらに裂くことで、ささみやシーチキンのような食感になります。
- 解凍し水切りした豆腐をほぐす際に少量の片栗粉を加えると、さらにまとまりが良くなり、肉らしさが増したから揚げや肉炒め風に仕上がります。
- ほぐし方も粗めや細かめに調整できるため、手でほぐしたり、より細かくしたい場合はブレンダーを使ってミンチ状やそぼろ状にして、ひき肉がわりにドライカレーやハンバーグ、肉団子風の料理にも適しています。
高野豆腐や凍り豆腐・湯葉代わりに

- 水分が抜けたことで、柔らかめの高野豆腐や凍り豆腐のようになります。
- 絹豆腐などは解凍後に層状で弾力が増して歯ごたえが生まれ、湯葉の代わりにも使えます。
- そのまま入れて煮るだけで、鍋・煮物や煮浸しに使え、味の染み込みやすく薄味でもふくよかな仕上がりになります。
- しっかり味を含ませる一品料理として、下味をつけたシンプルな豆腐焼きや豆腐ステーキなど、肉・厚揚げの代用品としても重宝します。
水切り済み豆腐として炒り豆腐・白和えに

解凍後にしっかり水切りを行えば、水分が抜けた豆腐として、炒り豆腐や白和えにも使いやすく、時短にもなります。
- 炒り豆腐の場合、しっかり崩して水切りすることで、調味料が染み込みやすくなり、旨味が増します。
- 白和えには、あらかじめブレンダーなどでほぐしてから冷凍し解凍したものを用いることで、適度に水分が抜けクリーミーさが際立ち、野菜や具材ともよく馴染むため、味わい深い一品になります。
豆腐がゆ風に
本来の豆腐がゆは、豆腐を米の粥のように仕立てたお吸い物を指します。
そのため、豆腐を米粒大にカットしてだしで炊くものですが、解凍後の豆腐を細かく崩してだし汁で煮込み、片栗粉でとろみをつければ、柔らかく優しい風味の豆腐がゆ風が手軽に作れます。
お好みにより卵でとじたり、生姜やネギを添えると風味豊かな軽食になりますよ。
湯葉煮に見立ててタコやキュウリなどと酢味噌で
解凍した豆腐を薄くスライスし、軽くだしで炊くかだし汁に浸けておくことで湯葉煮風になり仕上がります、
冷ましてタコやキュウリと合わせ酢味噌をかければ、さっぱりとした一品が楽しめます。
冷凍豆腐ピカタレシピ(2人分)

カット冷凍したものを使えば、手軽に作れて食感もアップしお弁当にも便利です。
粉末の鶏ガラスープやコンソメだし、カレー粉、粉チーズを下味として加えるアレンジもおすすめですよ。
材料
- 冷凍絹豆腐:1丁分(300g位)
- 卵:1個
- 小麦粉:大さじ2
- 塩・こしょう:少々
- オリーブオイル:適量
作り方
- 厚さ1cmにスライスして冷凍した豆腐を解凍し、絞ってしっかり水切りする
- 塩・こしょうを振り、小麦粉をまぶす
- 溶き卵にくぐらせ、中火で両面を焼き色がつくまで焼く
- ケチャップやウスターソースなどお好みの味を添えて完成
チーズ入りやき豆腐ナゲットレシピ(2人分)

肉なし、揚げずにチーズで生地をまとめてはんぺんでふんわり焼くタイプのナゲットです。
その他、シーチキン、コーンやミックスベジタブルなどを加えたり、パン粉をまぶしてから焼いても、ボリュームアップしながら軽めに食べられます。
材料
- 冷凍絹豆腐:1丁(300g程度)
- ピザ用チーズ:50g
- 片栗粉:大さじ2~3
- はんぺん:1枚
- ショウガ・コンソメパウダー・塩:少々
- オリーブオイルやサラダ油:適量
作り方
- 解凍した豆腐を水切りして手でほぐす、ほぐしたはんぺんとほぐしたはんぺんを加える
- ほぐしたはんぺん、片栗粉、チーズを混ぜ、ショウガ・コンソメパウダー・塩で味付けする
- 小さなボール状に丸め、フライパンで両面がきつね色になるまで焼く
蒸しナスの冷凍豆腐精進麻婆ソースがけレシピ(2人分)

あっさり食べたい時に、ひき肉を使わず冷凍豆腐をそぼろに見立てた麻婆ソースをナスにかけていただきます。ソースに長ネギを加えたり、片栗粉でとろみをつけても合いますよ。
材料
- 冷凍絹豆腐:1丁(300g位)
- ナス:2~3本
- 甜麺醤:大さじ1
- 醤油:大さじ1
- 水:適量
- 生姜・にんにく:各1片(みじん切り)
- ごま油:適量
作り方
- 豆腐を解凍し、水切りしてそぼろ状にくずす
- フライパンで生姜・にんにくを炒め、くずした豆腐を加えて火を通す
- 甜麺醤・醤油・水を加えて調味し、ひと煮立ちさせる
- ナスは乱切りや細長く縦切りし、ラップをかけて電子レンジ600wで3分程度蒸す
- ナスにソースをかけて完成
豆腐のかんたん基礎知識

概ね市販の豆腐は、食感が変化するものの、すべて冷凍はできるとわかりました。
さいごに主な4種類の豆腐について簡単に知っておくと、用途や食べたい気分に寄り添えるかもしれませんよ(他にもおぼろ豆腐やすくい豆腐などがありますが、今回は割愛しております)。
種類による製造方法の違いや特徴
絹豆腐
絹豆腐は、にがりを加えた豆乳を型に流し込み、そのまま固めたものです。
水分含有量が多く、なめらかな口当たりが特徴で、冷奴やスープ、煮物に適しています。
冷凍すると水分が抜けてスポンジ状や湯葉のような層状になりますが、その食感を活かした料理にも活用できます。
木綿豆腐
木綿豆腐は、豆乳ににがりを加えて固めた後、型に入れて圧力をかけ水分を抜いたものです。
しっかりした食感が特徴で、煮物や炒め物、揚げ物に適しています。
水分が少ないため、冷凍しても絹豆腐ほどの食感変化はありませんが、やや固くスポンジ状になり柔らかめの高野豆腐のようになることが多く、食感と味の滲み具合が増して肉代わりにもなり、食べ応えアップにつながります。
充填豆腐

充填豆腐は、豆乳と凝固剤を密閉容器の中で一緒に加熱し固めたものです。
食感は滑らかで柔らかく絹ごし豆腐に似ています。
容器から出さないままなら保存期限が長いのが特徴であるため、冷凍する機会は少ないかもしれませんが、冷凍すると絹豆腐と同様に水分が抜け、ごく柔らかめのスポンジ状や湯葉のような層状になります。
焼き豆腐

焼き豆腐は、木綿豆腐を表面がきつね色になるまで焼き上げたものです。
焼き目が付いているため、より硬さや形状を保ちやすく、風味が豊かで煮物や鍋物に向いています。
冷凍によりスポンジ状になりますが、焼き目の香ばしさが残ることを活かして、煮物以外に豆腐ステーキや丸めてから揚げにすると食べ応えもアップします。
まとめ

絹豆腐を冷凍すると、その食感が大きく変わり、これまでとは異なる新しい活用方法が広がります。
解凍後は元のような滑らかさは失われ、スポンジ状や湯葉のような弾力のある食感に変化しますが、この特性を生かすことで、味が染み込みやすくなり、そぼろ状にくずしたり大きくカットしたりとさまざまな形状にもできるため、煮物や炒め物、揚げ物など幅広い料理に適するようになります。
また、水分が抜けることで豆腐自体が凝縮されるため、味わいも深まるのが魅力です。
冷奴のようにそのまま食べるスタイルには向きませんが、調理方法を工夫することで、冷凍前とは違ったおいしさや食ベごたえを楽しめるのです。
なお、絹豆腐以外の木綿豆腐や充填豆腐、焼き豆腐なども冷凍が可能であり、それぞれの特徴を活かした使い方ができます。特に木綿豆腐は、柔らかめの高野豆腐のような食感や味滲みに変わるため、冷凍後もっとも料理に使いやすく重宝します(見づらいですが、上の写真は木綿豆腐を冷凍・解凍した断面で、穴が開きスポンジ状になっています)。
冷凍することにより料理のバリエーションが増えて、日々の食生活を豊かにするきっかけになりましたらさいわいです。
色々試しながら、手軽に新たな魅力を発見してみませんか。


