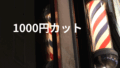食器類の購入時についてくるバーコードや商品ラベルのシール、きれいに剥がせれば問題ありませんが、べたつきや跡が残ってしまい、気になったことはありませんか?
そのままだと見た目もすっきりせず、使い心地も良くありませんよね。
そんな時、特別な道具を使わずに、家にあるもので簡単にシール跡を取り除く方法として、食器の素材を傷めにくく、すぐに試せるテクニックを6つご紹介いたします。
食器類のシール跡を消したい

シール跡が気になる理由
食器にシール跡が残ると、見た目が悪くなるだけでなく、ホコリや汚れが付着しやすくなります。
また、べたつきが手に付くことで使用感も悪くなり、洗浄時や扱う際に誤って落下や破損してしまう恐れもあるでしょう。
食卓で使用するアイテムとして、特に来客時にシール跡が残った食器を出すことは、見た目の印象が損なわれため避けようと考えると、せっかく購入したもののなかなか使用する出番がなくなってしまうのは、もったいないことです。
食器棚の中で、毎回シール跡や汚れに目がいくというのも不快ですし、キレイに消したいと思いますよね。
シール跡の種類とそのままにするリスク
シール跡には、紙が残ってしまうタイプや、透明なフィルムのみが残るタイプ、粘着剤だけがベタベタと残るタイプなどがあります。
いずれの場合も、そのまま放置すると、時間とともに固着して取り除きにくくなり、素材そのものを傷めてしまう原因にもなりかねません。
また、粘着剤が変化して黒ずみや黄ばみを引き起こすこともあり、自分では完全に除去するのが困難になる場合も生じてしまいます。
見た目の問題だけでなく、使うたびに不快な感触が残ることで、使用頻度が下がったり、結局新しい食器を購入する羽目になったりするケースもあるでしょう。
早めの対処で除去しやすいということは、多々ありますので、このあとの方法をお試しいただきたいです。
家にあるもので簡単除去と注意点
市販の専用クリーナーも便利ですが、手元にない場合は、まずは身近なアイテムで試してみたいものです。
家庭にあるもので手軽にできる方法なら、コストもかからずエコにもつながります。
たとえば、重曹やお酢、食用油などはどの家庭にもあることが多く、シール跡に効果的な手段として活用できます。
ただし、食器の素材によっては変色や傷の原因になることもあるため、選ぶ方法には注意が必要です。
特にプラスチック製の食器やコーティング加工されたものは、使用するアイテムや力加減によっては表面にダメージが生じることもあります。
どの方法にも共通して言えるのは、まず目立たない箇所でテストしてから本格的に行うことがコツになります。
次の章で具体的な方法を6つお伝えいたします。
簡単除去テクニック6選

少量に対しもっと簡単で定番の方法
購入後や未使用の状態で、まずはゆっくりシールをはがした後、部分的にごく少量シールや粘着剤が残ってしまったという場合も多々ありますよね。
その場合は、中性洗剤をつけて軽くこすったあとお湯で流すだけで、残りを除去できる場合が多いでしょう。併せて、材質によっては、スポンジの硬い面の方やアルミスポンジでやさしくこすると、より落としやすくなります。
また、セロテープを数回残った粘着部分にあて、付着させて除去する方法が最も簡単で、皆さんも行っていることでしょう。
その1:重曹を使ったシール跡の除去

重曹には、油汚れや粘着質を分解する作用があり、粉やペーストの状態で使用する場合が多く、軽い研磨作用もあります。
天然素材で特に台所まわりの掃除や脱臭にも活用されており、多用途に使える便利なアイテムといえるでしょう。
必要なアイテムと手順・注意点
【用意するもの】重曹、水、柔らかい布またはスポンジ、必要時ゴム手袋
- 重曹と水を1:1の割合でペースト状にする
- シール跡に塗布し、5〜10分ほど放置してなじませる
- 柔らかい布で円を描くようにやさしくこすって汚れを浮かす
- 水で洗い流し、最後に乾いた布で拭き取る
※陶器やガラスには適していますが、プラスチックの場合は表面を傷つける可能性があるため、目立たない部分で試してから行いましょう。作業中は強くこすりすぎないようにし、やさしく行うのがポイントです。
セスキ炭酸ソーダ
重曹と似た働きをする「セスキ炭酸ソーダ」もおすすめです。
より洗浄力と汚れの分解が期待でき、市販のスプレータイプはキッチン全体の掃除にも使える万能選手です。
使い方としては、セスキスプレーを跡に直接吹きかけて数分置き、布でやさしく拭き取るだけです。ご自宅に粉状のタイプがある場合は、ペースト状にして使用することも可能です。
その2:お酢を活用したシール跡の消去
お酢は、酸の力で粘着成分を分解して剥がしやすくしてくれます。
水垢もキレイにしてくれるため、ガラス製品や白い食器の洗浄やキッチンの掃除にも、日常的に取り入れやすいアイテムです。
においが気になる場合は、穀物酢やリンゴ酢などを使うと比較的マイルドになります。
手順と必要なアイテム・注意点
【用意するもの】お酢、キッチンペーパー、ラップ、布、ゴム手袋
- キッチンペーパーにお酢をしっかり含ませてシール跡に貼る
- 上からラップをかぶせて20〜30分ほど置いて浸透させる
- やさしく布でこすって粘着を落とす
- 最後に中性洗剤で洗い、においを取り除く
※酸に弱い素材には不向きな場合があるため、アルミ素材や一部の塗装面には使用を避けた方が無難です。長時間放置しすぎると変色の恐れがあるため、タイマーなどで時間管理も必要です。
その3:ドライヤーで温めて剥がす方法

シール跡に温風をあてることで粘着剤が柔らかくなり、剥がしやすくなります。
短時間・シンプルな方法で、温風はシールから5〜10cmほど離して数十秒ずつ当て、素材が熱を持ちすぎないように注意します。
熱に弱い素材(プラスチックなど)は、温めすぎると変形や変色を招く可能性があるため、避けた方が無難でしょう。
粘着剤が柔らかくなった状態でシールを剥がし、残った跡はセロテープや食器用洗剤で拭き取って水洗いましょう。
乾いた布で拭き上げるとツヤが戻りやすく、見た目もきれいになります。
また、シールが古く固着している場合は、うまく取り切れないこともあるため、重曹やお酢などと併用したり、状況に応じて組み合わせるのも一つの手です。
その4:家庭にある油を使用する方法

サラダ油、ごま油、オリーブオイルなど、日常の料理でよく使われる油には、粘着剤を柔らかくし、浮かせて除去しやすくする働きがあります。
食品であるため食器に使用しても問題なく、強いにおいが残らないのも使いやすいポイントです。
手順とポイント
【用意するもの】サラダ油、ごま油、またはオリーブオイルなどの油/コットンまたはキッチンペーパー/やわらかい布/食器用中性洗剤
- 油をコットンやキッチンペーパーに染み込ませる
- シール跡にしっかり貼り付け、油がなじむように15〜20分程度そのまま放置する
- 放置後、コットンを外し、やわらかい布でやさしく拭き取る
- 粘着剤が浮いてきたら、余分な油と一緒に丁寧に拭き取る
- 最後に食器用洗剤とぬるま湯を使って、表面の油分をしっかり落とす
頑固な粘着には、油をたっぷり使用し、ラップをかけて密閉することで浸透力が高まります。
小さな器であれば、全体をビニール袋に入れて処理する方法も、除去しやすくなります。
後処理をしっかりと
油が表面に残っていると、ホコリや汚れがつきやすくなるだけでなく、他の食器と接触したときにべたつきが移る可能性があります。
そのため、洗剤は中性のものを使い、泡立ててしっかりと全体を洗い流します。とくに細かい溝のある陶器やエンボス加工された食器は、油が残りやすいため、スポンジの先端などを使って丁寧に洗うとよいでしょう。
熱めのお湯を使うと油分が分解されやすくなり、すすぎもスムーズです。仕上げには布でしっかりと水気を取り、自然乾燥させてください。
その5:除光液の活用法
除光液は、マニキュアの除去に使われることで知られていますが、その溶解力でシール跡の除去にも活躍してくれます。
特に、ベタつきが時間とともに頑固になったシール跡に対して、スムーズに剥がすことができます。
使用手順および注意点
【用意するもの】除光液/コットンまたはティッシュ/ゴム手袋/柔らかい布/中性洗剤と水
- ゴム手袋を着用し、風通しのよい場所で作業する
- コットンに除光液をたっぷり含ませ、シール跡部分に押し当てるようにして湿らせる
- 1〜2分ほどそのまま放置し、接着剤が柔らかくなるのを待つ
- やさしく拭き取るようにして、粘着成分を取り除く
- 最後に柔らかい布で水拭きし、その後中性洗剤でしっかりと洗浄し、溶剤が残らないように仕上げる
色付きのプラスチックやプリント加工された食器に使用すると、表面が変色したりコーティングが剥がれたりする恐れがあります。必ず目立たない場所でテストを行ってから全体に使用するようにしましょう。
また刺激臭があるため、作業中は窓を開けるか換気扇を使用するよう留意しましょう。
その6:市販の剥がし液を使う
市販されている専用のシール剥がし液は、粘着成分を効果的に分解するために特別に配合されており、家庭にあるものでの対処が難しい頑固なシール跡にも強力かつスピーディに作用します。
主にジェルタイプとスプレータイプの2種類があり、それぞれ使い勝手や対象の食器素材に応じて選べるのが特徴です。ジェルタイプは粘度が高く、垂れにくいため垂直面や細かい部分へ、スプレータイプは広範囲に素早く塗布できる場合に便利です。
選ぶ際には、食器の素材に対応しているかどうかを、パッケージの説明書きや内容表示で必ず確認しましょう。ガラス製や陶器、プラスチック製の食器にそれぞれ適したタイプや、無臭タイプや低刺激タイプなどがあります。
いずれの場合も、必ず換気をしながら使用し、使用後はしっかりと水洗いして、食器に薬液が残らないようにしましょう。
シール跡を消す際の注意点とコツ

失敗を避けるためのポイント
まずは、すべての方法に共通するポイントをまとめました。
・最初に素材に合うか目立たない場所でテストする:思わぬ変色や傷のリスク回避に
・焦って力を入れすぎない:やさしく根気よくこすることが傷つかずに却って近道にも
・長時間放置しない:表面の劣化や変色を避けるためタイマーなどで時間管理を
・いくつかの方法を組み合わせる段階的でもOK:ドライヤー後に油や重曹ペーストなど
食器類の素材に応じた適切な方法
ガラス食器に最適なシール除去法
重曹やお酢、一部はドライヤーが適しています。
ガラスは比較的強いため、複数の方法を試しても傷みにくい素材で、粘着力が強めのシールには、重曹ペーストをなじませたり、お酢を染み込ませてラップで覆っておくことで、無理なくはがせる場合が多いでしょう。
仕上げには中性洗剤や油で拭き取り、しっかり水洗いするとよいでしょう。
プラスチック食器のための注意点
熱や薬品に弱いため、ドライヤーや除光液は避けるのが無難です。
油や中性洗剤を使った方法がおすすめで、油分を使って粘着をゆるませた後は、ぬるま湯と中性洗剤でしっかり油を取り除きましょう。
特にカラフルなプラスチック製品は色落ちや変色に注意が必要なため、時間をかけて行うのがコツです。
陶器食器のシール跡をうまく消す技
陶器は表面がややデリケートなものもあるため、強くこすらずに重曹ペーストもしくはセスキ炭酸ソーダを用いるとよいでしょう。
陶器には細かい凹凸があることも多く、シール跡が入り込みやすいため、丁寧にシールを剥がしたあとは、やさしく水洗いして、目に見えない洗剤残りや粘着成分をしっかり除去してください。
DIYとプロのサービスの違い

DIYではコストを抑えながら自分のペースで対処できますが、高級食器や長年放置した跡には専門業者のクリーニングも視野に入れるとよいでしょう。
プロのサービスでは、専用の機材や薬剤が使用され迅速に作業してもらえるため、思い入れのある贈答用食器やアンティーク品など、繊細な扱いが必要なものに対しては、無理せずプロの手を借りることも選択肢の一つです。
シール跡を消した後のケア方法
食器を長持ちさせるメンテナンス
除去作業が終わったあとは、中性洗剤を使って食器全体を丁寧に洗浄しましょう。
シール跡の処理に使用した重曹や油、除光液などの成分が残っていると、素材の変質やにおいの原因になることがあります。洗う際には柔らかいスポンジを使い、こすりすぎて表面を傷つけないように注意しましょう。
また洗浄後は、水気をしっかり拭き取り、風通しの良い場所で自然乾燥させたあと、柔らかい布やマイクロファイバークロスなどでやさしく拭き上げると、ツヤが戻りやすく、くすみ防止にもつながります。
特にガラスや陶器は、水滴の跡が残ると曇って見えることがあるため、仕上げの拭き取りは丁寧に行いましょう。
保管の際は直射日光を避け、なるべくホコリの入らない食器棚などの場所へ片づけておきましょう。
残った粘着物質のその他の取り方
シール跡を処理し中性洗剤で洗い流した後も、まだ微量のべたつきが残っているように感じることもあるでしょう。
こうした場合は、ベビーパウダーを薄くはたいておくことで、簡易的にべたつきを抑え、再度使用後に洗浄するという対処で、複数回洗浄すれば気にならなくなります。
また、仕上げにメラミンスポンジを使うのも一つの方法ですが、食器の素材によっては表面を傷つける恐れがあるため、力加減には十分注意してください。
最後の仕上げとして、材質にもよりますが可能であれば、あつめのお湯をかけたあと乾燥させるとスッキリ感を感じやすくなります。
食器類のシール跡を防ぐための工夫

使用前にできる対策
新品の食器を購入したら、なるべく早くシールを剥がしておくのがカギになります。
長時間貼ったままにすると粘着剤が劣化してしまい、時間が経つほどに固着して取りにくくなる傾向があります。
特に高温多湿な場所に保管していると、粘着剤が溶け出して広がったり、跡が残りやすくなったりします。
そのため、購入後は箱から取り出したタイミングで、できるだけ早めにシールを剥がしておくのが理想です。
もしシールをきれいに剥がしきる時間が取れない場合でも、ラベル部分にマスキングテープを貼っておくなどのひと工夫を加えることで、粘着部分の変化や汚れの付着を軽減することができます。
シール跡が残りにくい食器選び
シール跡を最初から避けたい場合は、購入段階で商品をよく確認することも大切です。
ラベルが貼られていない商品を選ぶのはもちろん、粘着力の弱いラベルや、水に濡らすと自然に剥がれる「水溶性ラベル」が採用されているブランドを選ぶという方法もアリではないでしょうか。
最近では、環境配慮型のパッケージとして、簡単に剥がせる再剥離タイプのシールを使用するメーカーも増えており、ユーザーからの評価も高まっています。
購入時には、価格やデザインだけでなく、こうした扱いやすさも選ぶポイントとしてチェックしておいてもよいかもしれませんね。
まとめ

まずは、ご家庭にあるものでできるシール跡対策から、試してみてはいかがでしょうか?
・食器のシール跡にはさまざまなタイプがあり、紙が残るものや粘着剤のみがべたつくものなど、見た目と洗浄時や扱い時の破損リスクなどに影響を与えるため、そのままにせず購入後できるだけ早く剥がしましょう。剝がしきれなかった部分が少量の場合は、洗剤とスポンジ類・お湯で、もしくはセロテープで取り除けることも多々あります。
・市販の専用商品がなくても、家にある重曹やお酢、食用油などを活用すれば、手軽に除去できる方法が多くあります。すぐに実践でき環境にもやさしい点が魅力です。
・重曹・お酢・ドライヤー・油・除光液・市販のシール剝がし液など、それぞれの性質を理解して使い分けることで、よりキレイに跡を取り除くことが可能になります。また、組み合わせて段階的に除去する方法もやさしい対処になります。
・素材別に、ガラス、陶器、プラスチックなどそれぞれに向いている手法を選ぶこと、目立たない箇所でお試しをすることで、変色や傷のリスクも回避しやすくなります。
・シールを剥がした後は、洗剤や熱湯などでしっかりと表面を洗浄し、丁寧に乾燥・保管することで食器の美しさもキープできます。
・かなり歳月が経過してしまった場合や、思い入れのある贈答用食器・アンティーク品など、繊細な扱いが必要なものに対しては、無理せずプロの手を借りることも選択肢の一つです。